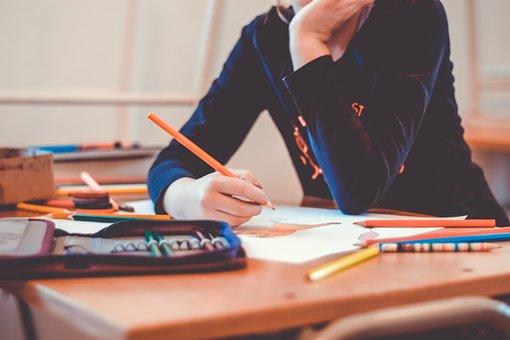【自律=能動】:【漫然=受動】
音羽教室の1指導は【WORK】と【FIX】で構成されます
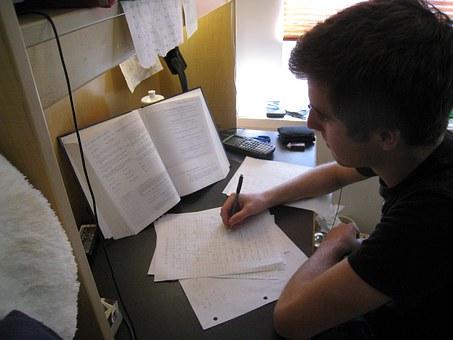
・【WORK】…指導:解説/説明
・【FIX】…練習:解問/定着
敢えて【FIX】を設定している目的は、先ず
「教わった内容」や「問題の解き方」を自力で実践する為です。
しかし、【FIX】には他の一面があります。謂わば【模擬自習】です。
社会人や成人であれば、例えば、『慎重』な作業を求められれば、
『慎重な作業』を行えます。それは既に実感として、
『慎重』と「普通」との《差》や《違い》を持っているからです。
「赤信号で停止」する様に、「慎重な作業が可能」になります。
『赤信号』や『慎重』と言う《記号》に正しく反応出来る訳です。
また、《記号》を履行できなかった後の「怖さ」も熟知しています。
では、もしも《記号》の持つ「意味」や「内実」、或いは「怖さ」を
知らなかったとしたら、いかがでしょう?。
実は【自習】や【見直し】等の《記号》にも同様の事が起こります。
【指示】⇒【行動】…その温度差

ご父兄諸氏や保護者の皆様には、上司や先輩から
「〇〇しておけ!」などと命じられ、
「〇〇するには、どうすればイイんだ?」と悩んだ…
そんな経験や過去をお持ちではありませんか?。
『自習して』とか『見直して』、更には『勉強して』まで含め、
実は生徒達や子供達も【類似の状況】下に居るのかも知れません。
『自習・見直し・勉強』等の《記号》の持つ意味や価値…或いは、
【具体的なアプローチ法】を持っていないかも知れないのです。
以前に比べて、恵まれた学習環境と豊富な学習ツール、それらは
時に『受動的で、工夫の無い、鵜呑み学習』への傾斜を深めます。
組織で若年の部下を持つ方には、或いは既知の事かも知れません。
【FIX】と【自習】

【FIX】では、問題自体は担当講師から与えられていますが、
《自力》で問題に取り組む姿勢は【自習】に通じる処が《大》です。
実際、前任の担当教室でも【FIX】に真剣な生徒達の多くが
【自習来校】の頻度が上がり、【結果】を出せていました。
【FIX】への取り組みが、その素地(体感)を造り、実のある自習を
実現します。逆に、『知らない』事は実行できないのが普通です。
「〇〇しなさい」と言う…その前に、【〇〇の雛型】を示す配慮や
視線の高さを生徒と合わせる様な《導入》も大切かと考えます。
「知識」や「技術」の伝達だけでは興味や意欲は育ちません。
そして、何年ものスパンで馴染んだ『深い色』を変えるには、
相応の《時間》、もしくは意識変化の《契機》が必要です。