早稲田育英ゼミナール
狛江教室
[2015年4月30日]
中学校数学編 〜定期テスト必勝法〜
「知って得するやって得する 〜定期テスト必勝法〜 」
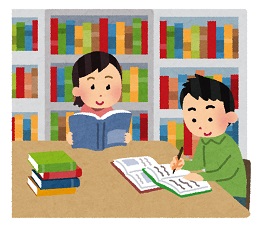 さて、世間でゴールデンウィークを迎え、お出かけする人、部活で忙しい人、家でリラックスする人、さまざまかと思います。
さて、世間でゴールデンウィークを迎え、お出かけする人、部活で忙しい人、家でリラックスする人、さまざまかと思います。
とはいえ、学生の諸君には「定期テスト」という関門が待ち受けています。休日の中であっても、学習の時間を確保して、テストに対して備えていきましょう。
1・定期テストの問題とは
学校の先生によって少しずつ問題の傾向は異なりますが、そこで問われているのは、授業にまじめに取り組んでいたか、授業内容をしっかり復習できていたかということです。
問題は、基礎的な問題・典型的な応用問題・先生のオリジナル問題などで構成されていますから、まずは自分の学力に応じて目標を決めて、どの問題まで解けるようにしておけばよいかをはっきりさせておきましょう。
?教科書から出る
テストの問題は基本的には学校の教科書やワークの問題と全く同じか、あるいは数字を変えた程度のものがほとんどです。
いろいろな問題集に手を出すのではなく、まずは、教科書やワークを使って問題演習を行うことが大切です。
?授業が基本!
授業中に扱った問題や宿題はテストに出題されやすいですから、学校での授業を真剣に聞いて、ノートをしっかり取っておきましょう。
また、授業や宿題の問題の中で、自分の力で解けなかったものには必ず印(○△×など)をつけ、しっかりと理解した上で、もう一度解きなおしてみましょう。
2・勉強するときには
わかることと解けることは違います。ただ解説を読んでわかっても、実際のテストでは解けないということはよくあることです。教科書やワークの問題を反復練習して、しっかりと自分のものとして身につけることが大切です。
?まずは重要公式の確認から
教科書やノートの中で、強調してある部分(アンダーラインや色分けなどしてあるところ)は重要公式や問題を解くうえでの注意点です。まずはこれらをしっかりと理解し、覚えることが大切です。
まとめノートを作ったり、何度か解き方をまねながら書いてみるのもよいでしょう。
?やさしい問題に落とし穴
数学のテスト勉強というと、すぐに難しい問題にあたり、わからなくなって、あきらめてしまう生徒がいます。これは、計算力が不足していたり、基本的な考え方や解き方が身についていないのが原因です。
問題に取り組むときは、まず易しい問題をたくさん解いて、しっかりと基礎力を身につけてから応用問題に進むようにしましょう。
?印が効果を発揮する
問題演習をするときは、解いた問題には必ず印をつけておきましょう(すぐに解けた問題には○,時間がかかった問題には△,間違えた問題や解けなかった問題には×・・・など)。問題の印が△や×のところは弱点となるところです。なぜ、間違えたのかを確認して、もう一度解きなおしておきましょう。時間がかかった問題は、速く・正確に解けるように練習をすることが大切です。
さらに、テスト直前に、×や△印の問題を再度解くことで高い効果が得られます。間違いなおし用のノートを作るとよいでしょう。
?数量分野は計算ミスに注意
数量分野の問題において、計算問題は得点源としやすいところです。たくさん問題を解くことも大切ですが、間違えた問題はなぜ間違えたかを確認し、同じミスを繰り返さないようにしましょう。
?図形問題はイメージが大切
図形分野は、得意・不得意がはっきり分かれるようですが、これは、基本的な問題を理解し、イメージとしてパターンをとらえることができるかどうかによります。
不得意な生徒は、まず基本的な問題を反復練習し、自分で図を描いてパターンをつかむようにしましょう。