早稲田育英ゼミナール
狛江教室
雑学201308
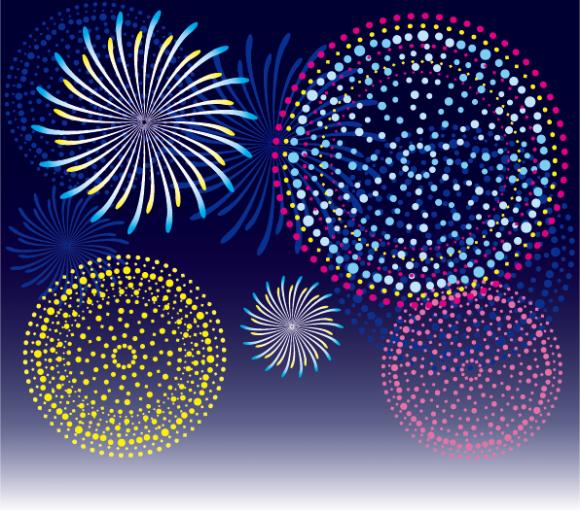
このコーナーでは、毎月ちょっとした豆知識を紹介していきます♪
今月は夏の昆虫についての特集です!
夏と聞いてカブトムシやクワガタムシを連想する人は多いと思います。
でも夏は、もっと身近なところでも多くの昆虫が元気になる季節です。
身近な夏の昆虫を、4種類だけですが紹介したいと思います。
●セミ

夏を代表する生き物は、セミではないでしょうか。
みなさんご存知のとおり、セミは成虫になってから1週間程度で死んでしまうといわれており、
寿命が短いと思われている昆虫です。
でも、実際には成虫になってから1ヶ月ぐらい生きているそうです。
そして、地面の下にいる幼虫の期間が種類によっては10年以上もあるという、
昆虫にしてはかなり寿命の長い方になります。
幼虫で過ごす時間が長いために
地表に出てくると嬉しいのではないかと思うくらいに、
セミは元気いっぱい大きな声で鳴きます。
ミンミンゼミ、クマゼミ、ヒグラシ、ツクツクボウシなど、
気にしていれば何種類かのセミの声を聞くことができます。
日本には、30種以上のセミが生息していると言われています。
旅先などで聞きなれないセミらしき声を聞くことがありましたら、初めて出会うセミの声かもしれません。
●バッタ

バッタが夏の虫だというイメージを持っている人は少ないかもしれません。
バッタの幼虫が出てくるのは春の終わりごろからなので、夏には元気なバッタが多くいるのです。
バッタの卵とか幼虫とか聞いても
イメージできない人が多いかもしれません。
外国には成虫のまま冬を越すバッタもいるそうですが、
日本のバッタはカブトムシと同じように
地面の中で卵のまま冬を過ごし、春になってから幼虫になり、成虫に育っていきます。
ただし、バッタは蛹(さなぎ)にはなりません。成虫と同じような外観の幼虫になるのです。
すごく身近な生き物なのに、バッタについて知らない人は大勢います。
「バッタが何を食べているのか、あなたは知っていますか?」
バッタは草を食べますが、虫かごなどで飼育するときには草だけではなく、水分補給にもなりますので
りんごなどの果物を切ったものも少し入れてください。
虫かごには土を入れ、乾燥してきたら霧吹きなどで湿らせるようにします。
秋になると、バッタは土の中に卵を産みます。
土が乾燥しないように霧吹き等で湿らせながら、
暖かい部屋の中に虫かごを置いておけば、
翌年の春の終わりごろには幼虫に出会えることでしょう。
●鈴虫

鈴虫は、耳に心地よい羽音で楽しませてくれると思うのはどうやら日本人だけだそうです。
多くの外国の方には鈴虫の羽音は「雑音」に聞こえるそうです。
私たち日本人は、鈴虫などの虫が出す羽音(鳴き声)や
日本庭園などにある「ししおどし」の音、風鈴の音などに
涼しさを感じることができる人種です。
何百年も前の書物などにも書かれていますので、
1つの国民性なのかもしれません。
「風流」とか「わびさび」とか、外国の方にはわかりにくいものが日本には多くあります。
でもこれらは、私たち日本人には大切なものだと思います。
日本人だから虫の音を楽しむことができる。
鈴虫は、何百年も前から日本人に飼われてきた、夏を彩る昆虫です。
●蛍(ホタル)

蛍はめったに見ることのできない昆虫だと思っている人は多くいらっしゃるようです。
「蛍を呼ぶ歌にあるように、
蛍というのはきれいな水の流れている場所に生息する昆虫だから、
きれいな川がないから近所にはいない。」と決めてしまっている人も少なくないようです。
でも、蛍を呼び戻そうと環境設備に取り組む人たちがいたり、
交通量の多い道路の横にある公園なのになぜか自然が残った一角があったりする場合などは、
身近なところで蛍を見ることができる場合もあります。
自然を壊して家を建てることが多い中で、
自然環境を整えるのはすごく大変なことだと思います。
しかし、何年にもわたる活動が実り、蛍が戻ってきたという地域もあります。
何十匹もの蛍が飛び交う風景というのは、感動的であり、しばし時間を忘れてしまうものではないかと思います。
蛍という小さな昆虫が、私たちに感動すら与える光景を作り出すのです。
見た人はきっと、昆虫のすごさにも驚いてくれると思います。
蛍が作り出す幻想的とも言える風景を見たことのない人は、この夏、蛍情報を集めて、近くの公園などに通ってみてはいかがでしょうか。
出会えるまではがっかりするどころか腹が立つくらいかもしれません。
でも、蛍が作り出す風景に出会えたら、きっと感動すること間違いありません。
| レベル | - |
|---|---|
| 目的 | - |
| 対象 | |
| 科目 | 今月のマメ知識(8月) |
| 期間 | |
| 授業形態 | - |
| 実施曜日 | |
| 実施時間 | - |
| クラス編成 | |
| 教材 |